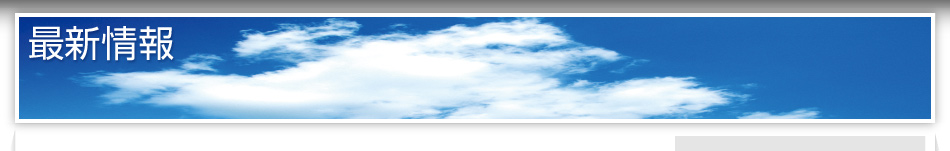
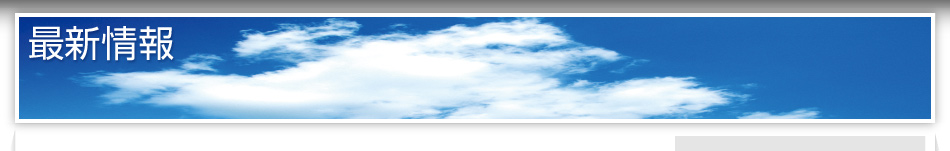
今年も残り僅かとなりました。
大震災、大雨などほんとうに大きな災害続きの年になってしまいました。これから何事もなく新しい年が来て欲しいものです。
ここ松本地方も、6月30日に発生した地震により多くの皆さんが被災されました。
税法にはそうした皆さんの税金を軽減する措置が講じられています。松本税務署でもこれから年末にかけて、罹災された方達向けの説明会が順次開催されます。
災害に伴う税の軽減措置には、所得を控除する「雑損控除」と、税を直接減額する「災害減免」制度の2種類がありますが、ここでは、より一般的な「雑損控除」制度についてご案内いたします。
○雑損控除とは?
災害(震災や風水害といった自然災害、火災などの人為的災害並びに害虫その他の生物による異常な災害等、自己の意思によらない不可抗力によって損害を受けるもの)、または盗難や横領により損害を被った場合、所得税の軽減を受けられる制度です。
○雑損控除が認められる資産の範囲
自己または生計を一にする親族が所有する資産のうち、日常生活の上で必要な資産に限られます。
《対象となる資産の主なもの》
住宅、家財道具、一般的な家電製品、自家用車、仏壇、墓石など
※自家用車については、専ら通勤や日常生活に使用しているものに限られ、スポーツカーやキャンピングカーなど嗜好性の高いものは対象にならない場合があります。
《対象とならないもの》
別荘、1個(1組)で30万円を超える貴金属や書画・骨董など日常生活に通常必要でない資産、棚卸資産や事業用の固定資産など
(事業用資産の損失は、事業所得の必要経費になります。)
○控除される金額
①(損失額-保険等で補填される額-所得金額)×10%
② 災害関連支出の金額-5万円
⇒①及び②のいずれか多い金額を所得から控除します。
※所得から控除する金額ですので、還付される金額ではありません。
損失額は、原則として時価により計算しますが、取得価格や使用年数により合理的に算定する方法も認められています。
【参考】雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」(国税庁資料)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/shotoku_03.pdf
また、災害関連支出の金額とは、原状回復費用(修繕費用)や被害の拡大を防ぐ応急措置や撤去、取壊しのための費用です。
○雑損控除を受けるための手続
被災した資産の取得時期や取得価格のわかる書類、取壊しや原状回復のために支払った工事代金の領収書、保険等により補填を受けた場合にはその金額がわかる書類などを添付し、確定申告書を提出することになります。
通常の雑損控除の場合、災害の発生した年度で所得控除を受けることになりますが、今回の震災の場合、特例として平成22年分又は23年分のいずれかの年度を選択して軽減措置を受けることができます(すでに平成22年分の確定申告を済ませている場合には、その申告を再計算し直す=更正の請求という方法で、納税した税金の還付を受けることも可能です。)
また、損失が控除しきれない場合、翌年以降5年間その損失を繰越すことができるので、節税には有効な手段です。ただし、雑損控除の対象となるかの判定や損失額の算出など、専門的な知識を要する部分も多いので、ご自身が該当するのでは?と思った方はお気軽にご相談ください。
事前にご連絡いただきますと、土日祝日の対応が可能です
Copyright © 飯塚肇税理士事務所 All rights reserved.